キュウリやスイカ、メロンを育てていたら、葉にぽつぽつと小さな穴が…それ、もしかして「ウリハムシ」の仕業かもしれません。
ウリ科野菜を好んで食害するこの小さな甲虫は、春から秋にかけて全国の畑に現れ、葉だけでなく果実や根まで狙ってくる厄介な存在。特に家庭菜園では、農薬に頼らずなんとか対策したいという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ウリハムシの生態や被害の特徴をわかりやすく解説しながら、酢・コーヒー・木酢液・アルミホイルといった身近なアイテムを使った無農薬でできる防除法を詳しく紹介します。さらに、ペットボトルで作れる捕獲トラップや、幼虫・卵への対策、効果的な捕まえ方のコツも解説します。
ウリハムシとは?
ウリハムシの生態、幼虫と成虫の特徴
ウリハムシとは、ウリバエとも呼ばれる体長7~9mmほどの小さな甲虫です。体の色は黄褐色で、頭部と前胸部は光沢のある橙黄色、翅はややくすんだ黄褐色をしています。幼虫はウジ虫のような淡黄色~白色の細長い虫で、成長すると約10mmになります。ウリハムシは主にウリ科植物(キュウリ、スイカ、メロン、カボチャなど)を食害する代表的な害虫です。
本州の場合ウリハムシの生活環は年1世代が基本です。成虫のまま集団で越冬し、春になって気温が上がると冬眠から覚めます。
越冬成虫は日当たりの良い草むらや石垣の隙間、落ち葉の下などに潜んでおり、平均気温が約17℃前後になる4月下旬頃から活動を開始します。春先にはまずソラマメやインゲン、ダイコン、ハクサイなどウリ科以外の作物の葉も食べ始め、5月頃からウリ科作物へ本格的に被害を与え始めます。
雌成虫はウリ科植物の株元近くの土中に卵を産みつけ、ふ化した幼虫は土の中でウリ科植物の根を食害しながら成長します。幼虫は地中で約3~4週間過ごし、土中で蛹になってから新成虫となり、7~8月に土から出てきます。そのため、5~6月と8月前後に被害のピークが訪れます。
越冬して翌年も発生する?
夏に出現した新成虫は葉や果実を食害しつつ、9月下旬以降になると徐々に越冬場所へ移動し、集団で冬越しします。なお、日本では多くの地域で年1回の発生ですが、温暖な地域では9~10月に第2世代の成虫が発生することもあり、被害が長引く場合があります。
ウリハムシの被害と初期症状は?

ウリハムシの成虫はウリ科野菜の葉を食害し、特徴的な食害痕を残します。葉脈を避けるように不規則な半円形~円形の穴を多数あけ、レース状(網目状)に葉をかじります。ときには同心円状に円を描く「輪食い」と呼ばれる食べ方をすることもあり、被害が進むと葉がボロボロになってしまいます。
春先にウリ科の苗が植わった直後から要注意で、4月下旬~5月頃には葉に小さな丸い穴が開き始めたらウリハムシ被害の初期症状と考えてよいでしょう。
小さな苗の段階で葉を食べ尽くされると生育不良となり、ひどい場合は苗が枯れてしまいます。成虫は日中に活動して葉の上にいるため、食害がウリハムシによるものでオレンジ色の小さな甲虫を確認できることが多いです。
近づくと素早く飛んで逃げるため「ウリバエ(瓜蝿)」とも呼ばれますが、ハエではなくハムシ科の甲虫です。
ウリハムシ成虫は葉だけでなく果実を食害する場合もあります。特にスイカやメロンの一種では、成虫が表面をかじって浅い傷を無数につけ、果皮に斑点状の食害痕が残ります。これにより商品価値が低下したり、傷から病原菌が入って病気になるリスクも高まります。また、花やつるの先端を食害することもあり、株の生長や着果に悪影響を与えることもあります。
成虫だけでなく、地中にいる幼虫も作物を食害します。幼虫はウリ科植物の根を食い荒らす害虫で、孵化直後は細かい根を、成長するにつれて太い主根や地際の茎内部まで食い進んでいきます。幼虫の食害は地上からは見えにくいですが、根をかじられた株は水や養分を十分吸収できず、生育が衰えていきます。
株がしおれたり、日中萎れる症状が見られたら、幼虫による根の被害が進行している可能性があり要注意です。特に6~7月頃、株が急に萎れて倒れてきた場合にはウリハムシの幼虫被害を疑ってみましょう。
また、幼虫は土中を移動して地面に接している果実に侵入することもあります。例えばスイカやカボチャの果実が土に直接触れていると、その接地面から幼虫が果実内に食い入ってしまうケースがあります。このような被害を防ぐには、果実と土の間に敷き藁やマットを敷いて直接果実が地面に触れないようにする工夫も有効です。
ウリハムシ被害の早期発見のポイント

ウリハムシ被害を初期に発見するには、苗の葉に小さな丸い穴が空いていないか日々観察することが大切です。また、朝や日中に葉の上や裏にオレンジ色の小さな甲虫がいないかチェックしましょう。
成虫は動きが素早いので、そっと近づいて静かに葉裏を見ると発見しやすいです。被害が軽微なうちに見つけて対処すれば、大発生を防ぎ作物へのダメージを最小限に抑えられます。
幼虫の被害は地上からは見えにくいですが、根をかじられた株は生育が衰えるため、急に株がしおれたり、日中の暑い時間帯に萎れる症状が見られたら、ウリハムシの幼虫による被害を疑いましょう。
無農薬でできるウリハムシ対策と防除法
家庭菜園ではできるだけ無農薬で害虫を防除したいという方も多いでしょう。ウリハムシは非常に厄介な害虫ですが、薬剤に頼らずとも工夫次第で被害を軽減できます。ここでは家庭菜園で実践しやすい無農薬対策をいくつかご紹介します。
こまめな捕殺による駆除が最も有効
無農薬栽培では人力での捕獲が重要です。ウリハムシ成虫は日中に葉の上で見つけやすいので、見つけ次第手で捕まえて駆除します。素手で捕まえにくければ、虫取り網で素早く捕まえたり、ガムテープの粘着面を葉に軽く当てて貼り付けて捕獲する方法も有効です。
特に朝の涼しい時間帯は虫の動きが鈍く、葉裏にじっとしている個体を捕まえやすいので狙い目です。毎朝見回って数匹ずつでも駆除すれば、被害拡大と産卵数の抑制につながります。見つけたウリハムシは確実に捕殺していきましょう。
食用酢

酢に含まれる酢酸の強い匂いはウリハムシが嫌う臭いであり、植物に近づきにくくしたり直接かけて弱らせたりする効果が期待できます。
手近な材料でできる手軽な方法ですが、酢単独ではウリハムシを完全に駆除するのは難しく、あくまで忌避効果が中心です。既に大量発生している場合や、土中の卵・幼虫にはほとんど効かないと考えられます。効果を高めるには他の対策と組み合わせることが重要です
また酢は酸性のため、高濃度のまま植物にかけると葉を傷めたり枯らしたりする恐れがあります安全に使うには、目安として食酢:水を1:1~1:2程度に薄め、夕方の涼しい時間に葉裏中心に散布するなど対応が必要です。土壌のpHを下げる可能性もあるため、過度の散布は避けたほうがよいでしょう。
コーヒー

使用済みのコーヒーや濃いコーヒー液も自然派のウリハムシ対策として注目されています。コーヒーに含まれるカフェインや植物由来成分の香りにはウリハムシへの忌避効果があります。ウリハムシは特定の強い匂いを嫌う習性があり、コーヒーの香りもその一つです。家庭にあるコーヒーを再利用でき、環境にも優しく土壌や野菜への影響が少ない点がメリットです。
もっとも手軽なのはコーヒー液スプレーです。濃いめに抽出して冷ましたコーヒーと水を1:1の割合で混ぜ、スプレーボトルに入れて葉や茎に吹きかけます。朝夕のウリハムシが活動しやすい時間帯に葉の表裏へまんべんなくスプレーすると効果的です。
またコーヒーかすを株元の土にまく方法もあります。乾燥させたコーヒーかすを株周りに薄く散布すると、土からコーヒーの匂いが立ち上って成虫の寄り付き抑制が期待できます。同時に土壌に有機物を補給できる利点もあるため、コーヒーかすの有効利用方法としておすすめです。
ただし、単独ではコーヒーによる忌避効果は限定的で、この方法だけで被害をゼロにするのは難しいでしょう。他の防除策(ネットや捕殺)と併用することで効果を発揮する補助的な手段と考えてください。
木酢液

木酢液は木材を炭化するときに出る液体で、独特の燻煙臭を持つ天然由来の防除資材です。ウリハムシ対策としても古くから利用されており、木酢液の香り成分が成虫にとって不快なため忌避効果を示します。
さらに木酢液は土壌中の微生物バランスを整え、作物を健全に育てる効果もあるため、結果的に害虫発生を間接的に抑えることも期待できます。
木酢液は必ず薄めて使うのがポイントです。原液のままだと濃度が高すぎて植物を痛める恐れがあるため、100倍程度(水1Lに対し木酢液約10ml)に希釈します。希釈液をスプレーボトルに入れ、ウリハムシが出やすい朝夕に葉や茎へ満遍なく散布します。週1回程度の定期散布や、雨で流れた後の再散布が効果維持に有効です。
木酢液だけでウリハムシを完全駆除するのは難しく、一定の忌避効果はあるが決定打ではないという位置づけです他の対策(防虫ネットや粘着シートなど)と組み合わせることでより効果を発揮します。
防虫ネット、トンネルの活用

ウリハムシの成虫が飛来し産卵するのを防ぐには、防虫ネットや不織布で物理的にシャットアウトするのが効果的です。特に幼苗期(苗が小さい時期)は被害を受けやすいので、定植直後から株全体をネットやトンネルで覆いましょう。
トンネル栽培の場合は、苗が十分成長し花が咲く頃までネット内で育て、受粉が必要になった段階でネットを外します。この間にウリハムシ成虫が産卵するのを防げれば、幼虫被害もかなり抑制できます。ネットは隙間なく設置し、出入り口もきちんと密閉することが大切です。
シルバーマルチ、反射資材
ウリハムシは銀色や白色の反射光を嫌う性質があるため、畝をシルバーマルチで覆うのも有効です。銀色ポリフィルムのマルチを使用すると、成虫の飛来自体を抑制できることが知られています。
シルバータイプの防虫テープを株の周囲に張り巡らせる方法も効果があるとされています。ただし、株が成長して葉が茂り、マルチの銀面が隠れてしまうと忌避効果が薄れるため、生育後半は葉を整理するか、別の防除策と併用しましょう。
こちらのシルバーマルチがリーズナブルでおすすめですよ↓
アルミホイル
アルミホイルを植物の株元に敷く方法は、物理的にウリハムシを寄せ付けない予防策として広く知られています。
ウリハムシを含む多くの害虫は強い反射光やキラキラ光るものを嫌う習性があり、アルミホイルを地面に敷くと太陽光を反射して成虫の飛来を抑制できます。シルバーマルチや反射資材と同様の効果が期待できます。
栽培環境の整備
ウリハムシの発生を環境面から抑制することも大切です。畑の周囲に雑草が茂っていると、そこが越冬や繁殖の温床となります。定期的に雑草を刈り取り、畑の周辺や株元を清潔に保つことで、ウリハムシの隠れ場所や産卵場所を減らせます。
また、植え付け時に株間を適度にとって風通し良く栽培することで、害虫が集まりにくい環境になります。ウリ科野菜を毎年同じ場所で作り続けるとウリハムシが蓄積しがちなので、他の科の作物との栽培場所ローテーションを行い、連作を避けるのも有効です。
コンパニオンプランツを活用

ウリハムシ対策として、コンパニオンプランツを利用する方法も有効です。中でも効果が高いとされるのがネギ類です。長ネギやニラ、玉ねぎなどのネギ科植物は独特の強い臭気を発しますが、このネギの匂いをウリハムシが嫌うため、ウリ科野菜と近接して植えることでウリハムシの飛来を抑制できるといわれています。
コンパニオンプランツとしてネギ類を用いる場合、効果を高めるコツはできるだけ近くに植えることです。植え付け穴に一緒にネギ苗を差し込み、根が絡むくらい近接させると高い効果が期待できると言われています。
ネギ以外では、マリーゴールドも忌避植物として有名です。マリーゴールドの強い香り成分をウリハムシが嫌うため、ウリ科野菜の近くに植えるとウリハムシを遠ざける効果があると言われています。マリーゴールドは土壌センチュウ抑制や他の害虫忌避にも使われる有用な花で、家庭菜園でも導入しやすいでしょう。
誘引トラップの利用
ウリハムシ成虫の習性を利用した誘引捕獲も効果的です。ウリハムシは黄色によく引き寄せられる習性があるため、畑に黄色の粘着トラップを設置すると飛来した成虫を効率よく捕獲できます。
市販の粘着式害虫トラップを支柱や杭につけて畑の周囲やウリ科作物の近くに立てておけば、誘引されたウリハムシがシートに張り付き、そのまま動けなくなるという仕組みです。被害が出始める前の成虫が飛来する時期に早めに設置しておくことがポイントです。
黄色の粘着トラップはこちらで購入できます↓
農薬を使わずにウリハムシの個体数を減らす手段として有効ですが、ウリハムシの密度が高いとトラップだけでは追いつかない場合もあるため、他の防除法と組み合わせて活用しましょう。
ペットボトルを利用したトラップ
市販の誘引トラップもありますが、身近な材料でウリハムシ捕獲器を手作りすることもできます。ウリハムシの成虫は危険を感じるとポロッと下に落ちて逃げようとする習性があります。この習性を逆手に取り、落ちた先で逃げられないようにするのがペットボトルトラップの狙いです。
- 透明な500mlペットボトルの上部をハサミやカッターで一周ぐるりと切り離す。
- 切り離したボトル上部を逆さまにして、胴体部分のボトルに漏斗状にはめ込む。上から入った虫が下に落ちても出口から逃げ出しにくい構造になります。
- ボトルの中に水を約1/3ほど張ります。できれば数滴の台所用洗剤を混ぜると表面張力が弱まって虫が浮かばず沈みやすくなります。
- ウリハムシの成虫を見つけたら、このペットボトル捕獲器を片手に持ち、虫にそっと近づけます。もう一方の手で葉を軽く揺すると、虫は驚いてポトリと落下し、そのまま漏斗を抜けて水の中に落ちる仕組みです
捕獲容器として使うことで、捕まえづらいウリハムシを効率的に捕獲できます。水ごと捨てれば処理も簡単なので、捕獲した虫の始末にも困りません。家庭菜園の範囲で、見つけ次第コツコツ捕まえる場合にはおすすめです。
忌避スプレー、ニームオイル
身近な材料で天然成分の忌避スプレーを作ることもできます。ニンニクや唐辛子の成分にはウリハムシの忌避効果があるため、これらをアルコールや水に漬け込んでスプレーにし、葉の表裏に満遍なく吹きかけます。効果の持続期間は比較的短いため、雨が降った後などはこまめに散布しなおしましょう。また、天然成分とはいえ葉が薬液で傷む可能性もあるので、初めは少量を目立たない葉でテストしてから使用するといいでしょう。
ニームオイルはウリハムシの食欲を抑制し成長を阻害する効果が報告されています。ニームオイルを薄めて葉に散布すれば忌避効果が期待できます。農薬を使用せずに天然成分で対策したい方にはおすすめです。
おすすめのニームオイルはこちらです↓
成虫、幼虫別の対策
成虫を効率的に捕獲するコツ

無農薬栽培では地道な捕殺が被害低減の決め手になる場合も多く、「見つけたらすぐ捕る」を心がけましょう。ウリハムシ成虫を手作業で捕まえて駆除する際のコツを紹介します。
- ウリハムシは気温が低い朝方や夕方には動きが鈍くなる習性があり、狙い目の時間帯です。特に早朝は夜露や低温の影響で葉にじっとしている個体が多く、このタイミングが捕獲のチャンスです。逆に日中暖かい時刻は素早く飛び回って逃げやすいため、朝のうちに畑を見回りして捕殺するのが効率的です
- ウリハムシは驚くとピョンと飛んだり下に落ちたりして逃げるため、素手で捕るのは意外と難しいです。
- 虫取り網を使って素早く掬い取るのが有効です。小型の網を使い、葉ごとさっと網で包み込むようにすると逃げられにくくなります。上述のペットボトルトラップを携帯して、それで受けるように捕まえても良いでしょう。
- ガムテープの粘着面で貼り付けて取る方法も有効です。
- いずれの場合も、ウリハムシは触ると落ちるという習性を念頭に、下に容器や網を構えてから刺激するのがコツです。
- 晴天時には素早く飛んでいってしまうこともあるので、日陰に入ったタイミングや複数人で挟み撃ちにするなど工夫しましょう。
成虫の数を減らすポイント
成虫の発生初期の数が少ないうちに集中的に捕殺することが、後々の被害拡大を防ぎます。見逃したペアが産卵すると次世代が増えてしまうため、「1日1匹たりとも逃がさない」くらいの意気込みで畑を巡回してください。
捕獲したウリハムシは確実に処分し、畑の外へ持ちようにします。地道な作業ですが、定期的な観察と早めの対策こそが被害を最小限に抑える鍵です。
幼虫、卵の対策

ウリハムシ被害を減らすには、成虫対策だけでなく土中の卵・幼虫への対策も重要です。成虫は葉を食べますが、幼虫は土中で根を食害し、気付かないうちに植物を枯らす原因となります。
卵から成虫へは約3~4週間と短く、暖地では年に複数世代発生するため、幼虫世代で食い止めないと次々繁殖して被害が拡大します。ここでは農薬を使わない卵・幼虫対策をいくつか紹介します。
- 防虫ネットで産卵を防止しましょう。ウリハムシは成虫が土の表面近くに卵を産みつけ、孵化幼虫が地中に潜って根を食べます。幼苗期から防虫ネットで株全体を覆い、成虫がそもそも株に近寄れないようにするのが効果的です。特に苗の植え付け直後~活着するまではネットで物理的に遮断することで被害を大幅に減らせます。
- 同時に地面にはマルチを施しておきましょう。黒マルチを敷くと地面への産卵場所を減らす効果があり、幼虫発生を抑制できます。またシルバーマルチなら成虫忌避と産卵抑制の二重の効果があります。
- ウリハムシは畑の残渣や周辺の雑草に潜みます。雑草を徹底的に処理し、越冬や繁殖の場を断つことが大事です。ウリ科作物の枯れたツルや根も放置せず片付けてください。
- 冬の間に畑を深く耕して天地返しし、土中の卵やサナギ・越冬成虫を地表に晒すのも有効です。寒風や天敵にさらされて生存率が下がります。
- 成虫を早期に減らし幼虫世代を作らせないことが最大の幼虫対策になります。
まとめ
ウリハムシはスイカやメロンなどウリ科作物を栽培していると悩みのタネですが、被害の特徴を正しく知り、早期発見・早期対策を心がければ十分に対策が可能です。
まずは日頃の見回りで初期症状(葉の小さな穴、甲虫の発見)を見逃さず、防虫ネットやマルチで物理的に防ぎ、コンパニオンプランツや誘引トラップを併用してで寄せ付けない工夫をしましょう。
雑草取りや連作を避けるなど畑の環境管理も非常に大切です。どうしても被害が多い場合には無理をせず適切な薬剤に頼ることも検討しましょう。
ウリハムシ対策は一つではなく複数の方法を組み合わせることが成功の秘訣です。今回紹介した対策を実践し、ウリ科野菜をウリハムシからしっかり守りましょう。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
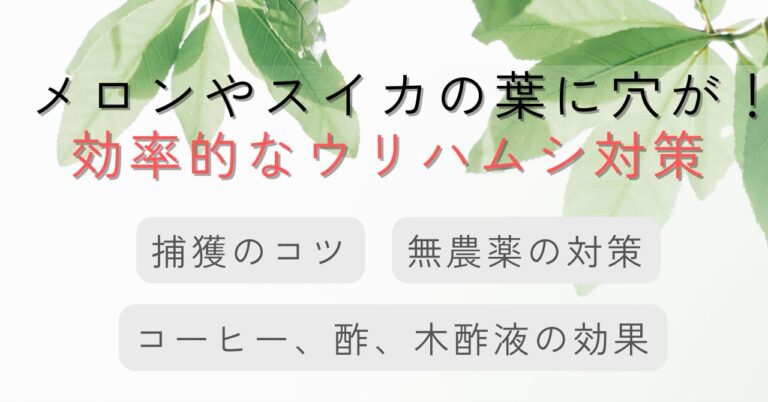

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/416c45f2.a01c262c.416c45f3.15b0a873/?me_id=1250472&item_id=10128194&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fplantz%2Fsale_img_250401-250430%2F4971910162453.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/476ae158.2a3beb2e.476ae159.29966c65/?me_id=1349517&item_id=10581992&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyoikenkou%2Fcabinet%2F2024w%2F4977292649049.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/476ae462.61b063a5.476ae463.aa173c38/?me_id=1223148&item_id=10000011&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fideshokai%2Fcabinet%2Fam003-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
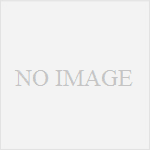
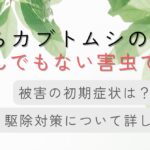
コメント