畑やプランターの土を掘ったらカブトムシの幼虫がでてきた!とびっくりした経験はないでしょうか。その幼虫、カブトムシではなくコガネムシかもしれません。
元気だった苗が急にしおれたり、ぐらぐらして枯れそうになっている…そんな異変の裏に潜んでいるのが「コガネムシ」です。地上を飛び回る成虫の影で、より深刻なのが土中でひそかに根を食い荒らす幼虫の食害。コガネムシは適切に対処しないと植物に致命的な被害を与えるやっかいな害虫なんです。
この記事では、コガネムシの生態と発生時期、見分け方から、無農薬でもできる具体的な駆除・予防法まで、家庭菜園で役立つ実践的な情報を徹底的に解説します。
コガネムシとは?
コガネムシの生態、特徴

コガネムシはコウチュウ目コガネムシ科に属する昆虫の総称で、日本には約360種が生息しています。本州から九州に広く分布し、北海道や南西諸島など地域限定の種もいます。成虫は体長1~3cmほどで丸みのある甲虫で、緑色や茶色など種によって色合いは様々です。
ライフサイクルは年1世代が基本です。多くの種では、夏(6~9月頃)に成虫が活動、産卵し、秋に孵化した幼虫が土中で越冬、翌春~初夏に蛹を経て成虫になるというサイクルを辿ります。
成虫は夜行性の種が多く、街灯など夜間に明るい場所へ飛来する習性があります。日中は葉の裏などに潜み、夕方以降に飛び回るものが多いです。
成虫は植物の葉や花、果実などを食害します。代表的な農作物としてはバラ科果樹(ブドウ、キウイ)、豆類(ダイズ、インゲンなど)、ナス科野菜(ナス、トマトなど)の葉や花を食べるものもいます。
幼虫は土中で生活し、植物の根を食べる根害虫です。幼虫はC字に丸まった乳白色のイモムシで、頭部が茶色く硬く、脚が6本あります。孵化した幼虫は地表近くの細根を食べ、成長すると太い根や芋なども食害するようになり、晩秋には地下20~30cmまで潜って冬を越します。
コガネムシの発生時期とライフサイクルは?

地域差もありますが、一般的に本州中部だと成虫は梅雨明け頃から夏に発生し、秋までに卵を産みます。暖地では活動期間が長く、寒冷地では活動時期が短めです。
いずれも夏~秋に産卵するため、秋口に幼虫が発生し始めます。なお、種類によってはライフサイクルが2年にわたるものや、春先にもう一度成虫が出現するものもいますが、家庭菜園で問題となる腫の多くは1年1世代型です。
【春(4~5月)】
越冬した幼虫が活動再開
(根を食べて成長)
↗ ↘
【冬(11~3月)】 【初夏(6月頃)】
幼虫は土中深く 幼虫が蛹に
潜って越冬休眠 成虫へ羽化
↖ ↓
【晩夏~秋(7~10月)】 ← 【夏(6~8月)】
卵が孵化し幼虫が 成虫が飛来・交尾・産卵
土中で根を食害 (葉や花を食害)
幼虫による食害と症状

コガネムシ被害は主に幼虫による地下部の食害です。成虫による葉や花の食害は目立つため見つけやすいものの、土中の幼虫による根の食害は発見しづらい上に植物の致命傷になります。
幼虫は鉢土や畑土の中で細い根や新しい根を食害します。被害を受けた植物は養分、水分を吸収できず水切れ状態になり、充分に水を与えても萎れや葉色不良が生じます。
進行すると生育不良や黄化、最悪の場合は枯れてしまいます。肥料を追加しても根が吸収できないため効果がなく、むしろ根を損傷した状態で肥料過多になると根腐れを招くため逆効果です。
食害の初期症状と早期発見のコツ
被害の兆候として、株元を揺らすとグラつく場合は幼虫に根を食われている可能性が高いです。また十分に水を与えているのに萎れる、生育が急に鈍化する場合も要注意です。
鉢植えでは土の表面にコガネムシ成虫がもぐり込んだ痕跡(土が掘り返されたような穴がある)や、小型のフン粒(細長い楕円状の土団子)を幼虫が排出して地表に出すこともあります。
どんな植物が被害に遭いやすい?

コガネムシ類の被害はあらゆる植物で起こりえますが、標的になりやすい作物には以下のようなものがあります。
- 夏野菜類: ナス、ピーマン、トマト、スイカなど果菜類は成虫にも幼虫にも狙われます。成虫は葉や花をかじり、幼虫は根を食害します。イチゴなどベリー類も幼虫被害を受けやすいです。
- マメ類: ダイズやインゲン、ラッカセイなど。成虫が葉を食べ幼虫が根をかじります。
- イモ類・根菜類: サツマイモ、ジャガイモなどは幼虫が地下部を食害しやすく注意が必要です。特にサツマイモは幼虫による被害が多いです。またニンジン、ダイコンなどの根菜も土中の幼虫にかじられることがあります。
- 果樹・花木: ブドウ、キウイフルーツ、ブルーベリー、バラなどは成虫が葉や果実を食べ、さらに土中に潜って根元に産卵されると幼虫によって根が被害を受けます。バラの鉢植えはコガネムシ幼虫被害で枯れやすいく注意が必要です。
- 芝生: 芝生、クローバー等はコガネムシ類の幼虫が好んで食害します。広い芝地では幼虫が根を食い切って芝が部分的に枯れる「斑枯れ」が生じます。
- その他、屋外で土に植わっている植物なら基本的に何でも標的になりえます。
上記のように幅広い植物が被害を受けますが、とりわけ鉢植え果樹(ブルーベリーなど)やプランター野菜は幼虫の溜まり場になりやすいため、植物の様子を観察し、異変があればすぐ対処しましょう。被害はあらゆる植物で起こりますが、柔らかく有機質の多い用土は幼虫が好む環境であるため特に鉢植えやプランターは狙われやすいです。
畑で発生した場合は作物以外に周辺の様々な植物があるため被害が分散される傾向にありますが、プランターに発生した場合は限られたスペースで植物の根を食い尽くしてしまうため被害が急激に大きくなる傾向があります。
また食害される部位として、野菜や花では主に根が食害され株の成長に影響しますが、サツマイモなど地下にできるイモ類ではイモ自体が囓られてしまうため要注意です。
天敵はいる?無農薬栽培に活用できるものも?

自然界ではコガネムシの幼虫を捕食したり、寄生する天敵が存在します。
- 鳥類
地表近くにいる幼虫はカラスをはじめ野鳥に掘り出されて捕食されます。家庭菜園でも、秋冬に畑を耕すとカラスやムクドリが幼虫をついばむ様子が見られます。また成虫もスズメやヒヨドリなどが捕食します。
- 哺乳類
モグラは主食のミミズに加え、地中のコガネムシ幼虫やネキリムシも捕食します。ただしモグラは畑を荒らす害獣扱いもされるため、共生は難しいかもしれません。
- 土壌性の小動物
ムカデやアリも幼虫を餌にします。特に大型のムカデは土中の白い幼虫を見つけて捕食しますし、アリも卵や孵化直後の小さい幼虫を襲うことがあります。
- 甲虫類
ゴミムシ類の一部やコガネムシ科内の肉食種は、土中でコガネムシの幼虫を捕食します。またヒラタアブの幼虫なども、地中浅くにいる小幼虫を食べる場合があります。
- 寄生バチ・寄生バエ
土中の幼虫に産卵・寄生するハチも知られています。ツチバチ科のハルコツチバチやマメコガネツチバチはコガネムシ幼虫に産卵し、孵化幼虫が内部からコガネムシを食べます。成虫に対してはヤドリバエ科のマメコガネヤドリバエが成虫に卵を産み付け寄生することが知られています。
- 微生物病原
乳化病菌と呼ばれる細菌がコガネムシ幼虫に感染すると、体内で増殖し数週間で死亡します。感染幼虫の体色が白濁するため「乳化病(ミルク病)」とも呼ばれ、微生物農薬として利用されることもあります。また一部の昆虫寄生性線虫はコガネ幼虫に寄生し駆除に利用できることが知られています。
昆虫寄生菌や線虫の中には生物農薬として市販されるものあり、作物の栽培に利用することもできます。こうした製剤は化学農薬に比べ即効性は劣りますが、環境中の天敵微生物を増やすことで継続的な効果が期待できます。
自然界における天敵はコガネムシの増加を防いでくれる効果は期待できるものの、これだけで土中から幼虫を完全駆除するのは難しいでしょう。他の駆除方法と組み合わせて対策していくのがおすすめです。
カブトムシの幼虫に似てる?カナブンとの見分け方は?
幼虫の見分け方
| 幼虫の種類 | 見た目 | 移動方法 | 生息場所 | 食性・被害 |
|---|
| コガネムシ | 白~乳白色の胴体、褐色の大きめの頭(C字形、体長約2~3cm) | 腹ばいで脚を使って速く歩く | 花壇土やプランター土など肥沃な土中 | 植物の根を食べる |
| カナブン | 白色の胴体、薄茶色の小さい頭 | 背面を下に腹面を上にしてゆっくり波打ち歩き | 山地の腐葉土・堆肥中(一般の庭土では稀) | 腐葉土や朽木を食べて分解する益虫 |
| カブトムシ | 太く太鼓腹型の白い胴体、大きく濃褐色の頭 | 腹ばいでゆっくり歩く | 腐植に富む深い土中 | 朽木・腐葉土を食べて分解する益虫 |
コガネムシ幼虫は白~乳白色の太い胴体に、濃い褐色の頭部を持ちます。体長は成長しても約2~3cm程度で比較的小型です。普段はC字に丸まっています。
対してカナブン幼虫は白っぽい胴体に淡い茶色の小さな頭部。頭部はほぼ体に埋まり込むほど小さく、頭部すぐ横に斑点状の模様が見られることが多いです。コガネムシ幼虫に似ていますが、全体的に細身です。
最も簡単な見分け方としては、移動方法を見るようにしましょう。コガネムシが腹面を下にして脚を使い移動するのに対して、カナブンは腹面を上に向けて脚はほとんど使わず、体全体をうねらせて前進します。
カブトムシ幼虫は体長6~8cm程度になるものもあり、明らかにコガネムシより大型ですので大きさで判断するのがよいでしょう。
カナブン、カブトムシとも朽木、腐葉土を好んで食べるため、家庭菜園の土から出てくることはまずありません。栽培場所で白っぽいC字型に丸まった幼虫が出来てきたら、まずコガネムシの幼虫と考えて良いでしょう。
いずれにせよ、土から幼虫が出てきたら種類を問わず即駆除するのが無農薬菜園の鉄則です。
コガネムシ成虫とカナブンの違いは?
| 特徴 | カナブン | コガネムシ | ハナムグリ |
| 体の形 | やや平たい長方形 | 丸みを帯びずんぐり | やや平たい長方形 |
| 羽の付け根の形 | 背中中央に綺麗な逆三角形(小楯板) | 半円状(楕円を半分に切った形) | 綺麗な正三角形 |
| 体色 | 緑色・青・茶など様々(光沢あり) | 主に地味な緑色や茶色 | 黒や緑に白い斑点模様 |
| 飛び方 | 上翅(硬い羽)を閉じたまま飛ぶ | 上翅を広げて飛ぶ | 上翅を閉じたまま飛ぶ |
| 好む場所 | 樹液や果実のある樹木周り | 草花の葉上や地際付近 | 花の上・花の中 |
「コガネムシ」と間違われやすい昆虫に「カナブン」や「ハナムグリ」がいます。見た目がよく似ていますが生態は大きく異なり、カナブン・ハナムグリはむしろ植物にとって益虫とも言われます。
成虫を簡便に見分けるには、羽の付け根の形をみるのがおすすめ。コガネムシは羽の付け根が半円状になっています。
カナブンとハナムグリは飛び立つ時に上の硬い羽を開かず、そのままブーンと飛ぶ独特の飛び方をします。一方、一般的なコガネムシはテントウムシのように硬い羽を広げて飛びます。
また、カナブン類は成虫が主に樹液や腐った果実を舐め、幼虫も腐葉土や堆肥を食べて育つ腐食性で、植物を加害しない点もコガネムシとの違いです。緑色の甲虫=すべて害虫とは限らないことに注意しましょう
成虫の駆除や防除対策
コガネムシ対策の基本は、成虫を捕殺して産卵させないことと、土中の幼虫を駆除、予防することの2つです。家庭菜園では手作業と工夫で対応できる方法が多々あります。
成虫の捕殺(手取り駆除)
コガネムシ成虫は動きが鈍い早朝や日暮れ時に捕まえやすいです。葉にとまっている成虫を見つけたら軍手をはめて捕まえるか、枝を揺すって落として捕殺します。
成虫1匹が数十個の卵を産む可能性があるため、見つけ次第捕らえることが幼虫被害の抑制につながります。飛んで逃げられないよう、下にシートを広げて揺すり落とすのも有効です。
どうしても手で触りたくない場合は、虫取り網やガムテープで捕獲するのがおすすめです。
防虫ネットの活用
成虫が飛来して産卵、食害するのを物理的にブロックする方法です。株元の土壌表面を防虫ネットで覆うと、成虫が土中にもぐって産卵するのを防ぐことができます。
特にプランターや鉢植えでは土の上に目の細かい防虫ネットを敷いておくと効果的です。成虫は小さな隙間からも入り込むため、プランターの外周を隙間無くネットで覆うよう工夫しましょう。
また、苗や株全体をで覆っておくと成虫の食害から守ることもできます。プランターの場合、このような丸ごと覆うタイプの防虫ネットだと非常に効果的です↓↓
防虫ネットは産卵防止に抜群の効果があり、幼虫発生を大幅に抑制できます。栽培の初期から使用し、成虫の産卵をシャットアウトしましょう。
マルチング
成虫が産卵しにくい環境を作る工夫です。例えば鉢植えや花壇の表土に小石や砂利を厚さ2~3cm敷き詰めると、成虫が土にもぐりにくくなります。
プランターなら、このような赤玉土を厚めに敷き詰めるのもおすすめです↓
バークチップやウッドチップで覆う方法もありますが、有機マルチは湿気を保ち逆に害虫にとってよい環境になる可能性もあるので、小石などの硬い無機質で覆う方が効果的でしょう。
家庭菜園によく利用される稲わらや黒マルチフィルムではコガネムシ産卵抑制効果はあまり期待できないため注意しましょう。
幼虫の対策
植え付け前に土壌をよく耕す

栽培を継続していた土壌にはコガネムシの幼虫や卵が残っていることが良くあります。気づかずに翌シーズンに苗を植え付けてしまうと、根を食害され植え直しになってしまうことも。
植え付け前に、畑やプランターの土をよく耕して卵や幼虫を駆除しておきましょう。幼虫を物理的に取り除くだけでなく、よく耕すことで土中の幼虫が傷ついて間接的に駆除する効果もあります。特に、前シーズンに植え付けた作物が枯れてしまったり、コガネムシの被害があった場所では必須の作業です。
太陽熱消毒
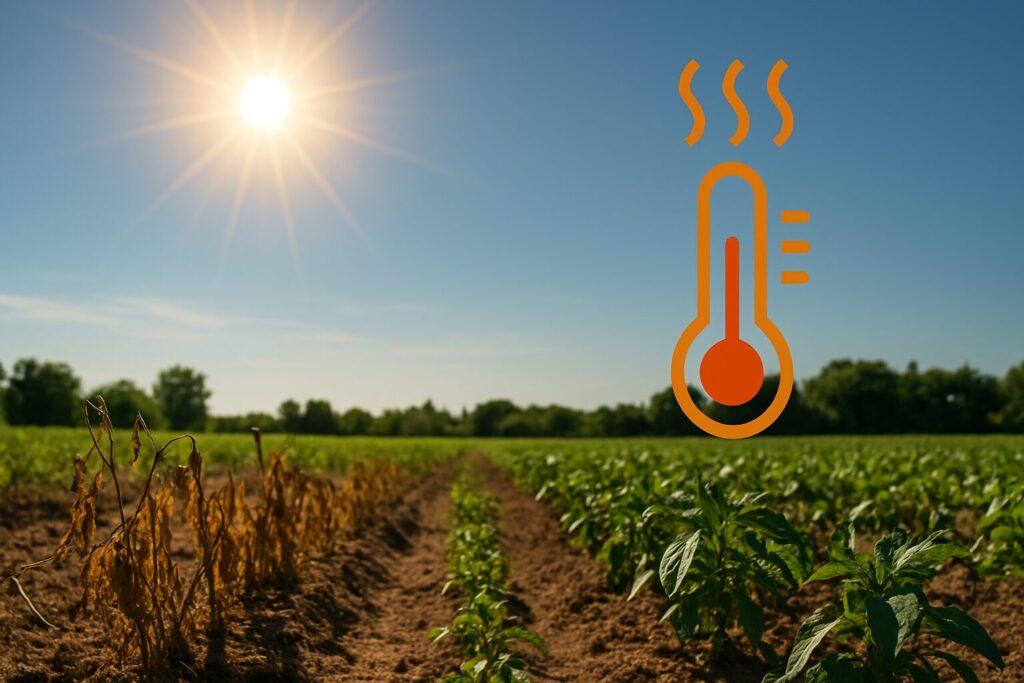
物理的に幼虫を駆除する方法は有効ですが、すべて取り切るのは難しいですし卵をすべて駆除するのは不可能です。
卵を含めて土壌の幼虫を駆除する方法として、太陽熱消毒が非常に有効です。
6月後半~8月ころの高温期に、栽培の終わった土壌にたっぷりと散水し、透明マルチフィルムを敷いて一ヶ月ほど放置しましょう。マルチフィルムの中が高温の蒸し焼き状態となり、コガネムシの卵や幼虫を効率よく駆除することができます。
太陽熱により内部の温度がしっかり上がるよう、必ずこのような透明のマルチシートを使用しましょう↓↓
夏場しか行えないのがデメリットですが、幼虫や卵駆除に非常に効果的な方法です。
寒起こし
1-2月の厳寒期に土壌を掘り起こし冷気に当てることで、害虫や有害微生物を駆除したり土壌環境を整える方法です。
寒い起こしのやり方についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。
米ぬか

米ぬかにはコガネムシ幼虫の成長を阻害したり忌避したりする成分が含まれていると言われ、無農薬農家で活用されています。土壌改良も兼ねて畑にすき込む方法で、播種前に10㎡あたり1~2kgを土壌全面に混ぜこみ、栽培中も1㎡あたり50~100gを定期的に土表に撒くと効果的とされています。
米ぬかの発酵臭や独特のにおいが産卵を抑制し、土表に層を作ることで幼虫の移動も妨げます。米ぬかを混ぜ込むと発酵に伴い熱を出すため、植え付け直前に使用するのは避けるようにしましょう。また、米ぬか施用時はカビが発生しないよう軽く混ぜ込み、カビ臭が強い場合は避けてください。
コーヒーかす

出がらしのコーヒーかすも有効活用できます。コーヒーかすにはカフェインとタンニンが残留しており、これらが幼虫の神経に作用して成長を阻害する効果があると言われています。
乾燥させたコーヒーかすを土に混ぜ込むか、鉢植えの表面に敷くことで忌避効果が期待できます大量に入れすぎると発芽抑制になる恐れがあるため、用土全体の5%程度を目安に混ぜると良いでしょう。
木酢液

木炭や燻煙の副産物である木酢液は、刺激臭で幼虫を忌避・殺虫する働きがあります。原液のまま使用すると刺激で植物が枯れてしまう可能性もあるため、100~200倍程度に水で希釈して使用しましょう。
植え付け前の土に散布してすき込むか、幼虫が増えやすい春・秋に株元土壌へ散布すると効果的です。注意点は濃度が高いと植物の根を傷めるため希釈倍率を必ず守ること、また植物によっては木酢液に敏感な種類もあるので事前に試すことです。
石灰資材
消石灰や苦土石灰も土壌害虫対策に併用されることがあります。石灰はアルカリ性であり、適量散布すれば土壌を中和して有用菌が増え、間接的に害虫が減るという考えですコガネムシ幼虫への直接の殺虫効果は限定的ですので、石灰だけでなく他の資材と組み合わせて総合的に改善するのが良いでしょう。
コンパニオンプランツ
ネギ類(ニラ、長ネギ、ニンニクなど)は強い臭いでコガネムシ成虫を寄せ付けない効果があります。ニンニクを混植したり、ニラやネギを畝の周囲に植えたりすると忌避効果が期待できます。
同様にハーブ類(ミントやバジル、マリーゴールドなど)も虫除け効果がある程度期待できます。
ニームケーキ、ニームオイル
インドセンダン(ニーム)の種子から取れるニームケーキは、有機栽培で土壌害虫抑制によく使われます。アザディラクチンという成分が昆虫の摂食を抑える作用があり、幼虫忌避効果が報告されています。
培養土にあらかじめ混ぜ込んだり、株元に撒いて水やりすると徐々に有効成分が浸透します。ただし即効ではないため、他の手段と組み合わせましょう。
またニームオイルは成虫の忌避や産卵抑制に効果が期待できます。希釈して葉に散布すると、成虫の食欲を減退させる働きがあります。
おすすめのニームオイルはこちらです↓
プランターや鉢の土に幼虫がいた場合の対処

プランター菜園では、土を掘り返した時にコガネムシの幼虫が出てくることがあります。鉢植えの植物が水をやっているのに元気がなかったり、株がグラつく時はまず幼虫被害を疑ってみましょう。
幼虫の除去
まず被害株を鉢から抜き、根鉢を崩して目視で幼虫を探し全て取り除きます。土の中から白い幼虫が出てきたら、逃さず捕殺してください。1匹見つかったら周囲に複数いる可能性が高いです。根にしがみ付いている場合も多いので、手で丁寧に取りましょう。
水に漬け込むのは幼虫を落とす効果はありますが、完全な駆除にはならないので必ず捕殺してください。
土の処理
幼虫がいた培養土は、そのまま戻すと卵や見落とし幼虫が残っている可能性があります。可能であれば新しい用土に交換するのが安全です。
古い土はビニール袋に入れて口を閉じ、夏場なら直射日光で高温消毒します。黒いゴミ袋に入れて数日間炎天下に置けば、大抵の幼虫は死滅します。
植え直し
幼虫を除去し土を処理したら、植物を元の容器に植え直します。傷んだ根は剪定してから、新しい用土か消毒済みの用土で植え付けましょう。
植え替え後は株がぐらつかないようたっぷり灌水し、用土を根に密着させます。株が弱っている場合、葉を適度に間引いて蒸散を抑え、半日陰で管理すると回復しやすいです。
植え直した後も油断は禁物です。鉢底から再度幼虫が出てこないかしばらく注意します。鉢植えでは土の量が限られるため、卵→幼虫への移行も比較的短期間で目に見えることがあります。数週間しても異常なければ、とりあえず大丈夫でしょう。
防虫ネットやマルチングで再発防止
今後同じ鉢で産卵されないよう、鉢土の表面を防虫ネットや不織布で覆うか、小粒の赤玉土や砂利で厚めにマルチングしておくと良いです。
またプランターを屋外に放置するのではなく、可能なら成虫飛来期だけ軒下や室内に避難させるのも手です。さらに定期的に鉢底から土を少量取り出し、幼虫やその糞が無いかチェックする習慣をつけると早期発見につながります。
プランター栽培ではコガネムシ幼虫は天敵が入り込みにくいため大発生しがちです。発見したら根こそぎ退治するつもりで、土替えも辞さない対処をしてください。それでも株が弱って回復しない場合は、残念ですが諦めて処分し、同じ土を他の鉢に使い回さないよう注意しましょう。
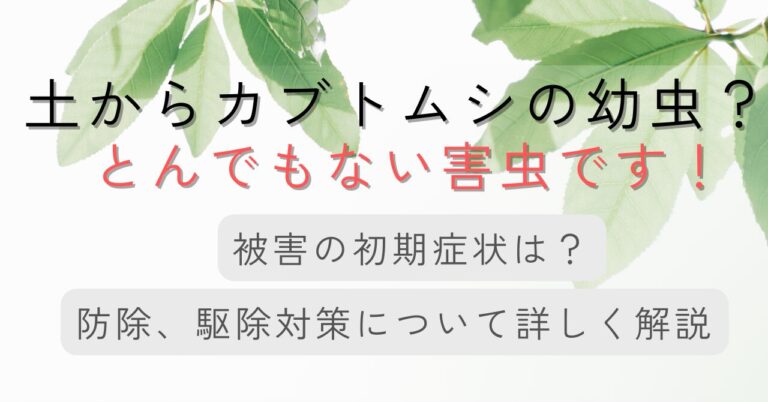

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/401e4f65.76891d64.401e4f66.73fb631a/?me_id=1260467&item_id=10000898&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarsol-morishita%2Fcabinet%2Fshouhinn%2Fbouchuu%2Fimgrc0090950323.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a9c7a0.16849ec2.47a9c7a1.8bbcaac3/?me_id=1231595&item_id=10000453&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fplanto-iwa%2Fcabinet%2F01844984%2F02942892%2Fsyosuei.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4052bfe2.bb3cf90b.4052bfe3.8d853a0a/?me_id=1230952&item_id=10013719&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnou-nou%2Fcabinet%2Fitem0106%2F0106100000015.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
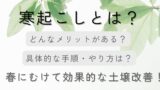
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/476ae462.61b063a5.476ae463.aa173c38/?me_id=1223148&item_id=10000011&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fideshokai%2Fcabinet%2Fam003-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
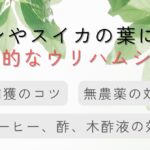
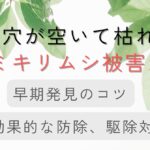
コメント